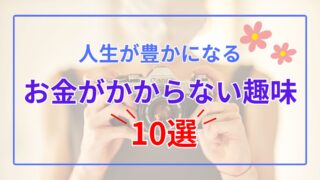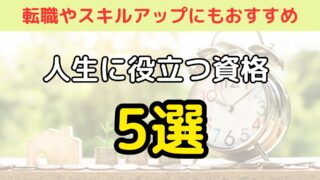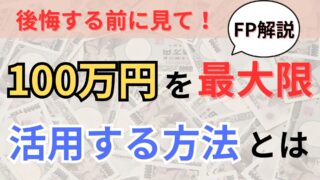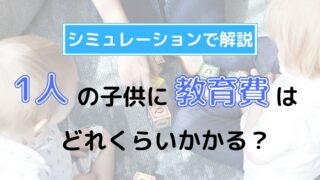1. 住宅ローン借り換えとは?まずは基本をおさらい
1-1. 住宅ローンの借り換えとはどういう仕組み?
住宅ローンの借り換えとは、現在返済中の住宅ローンを、より条件の良い別の金融機関のローンに切り替えることを指します。借り換えを行うことで、主に「金利を引き下げて月々の返済額を減らす」「総返済額を抑える」「返済期間を短縮する」といったメリットが期待できます。特に、金利が高かった時期にローンを組んだ人にとって、現在の低金利のローンに乗り換えることで、大きな節約になるケースも珍しくありません。
1-2. なぜ借り換えで「お得」になるのか
住宅ローンの返済額は、借入額、金利、返済期間によって決まります。そのため、金利が1%違うだけで、数十万円〜数百万円の差が生まれることもあります。例えば、3,000万円を35年ローンで借りていて、金利が2.0%から1.0%になると、総返済額が600万円以上変わります。ただし、借り換えには新たなローン契約に伴う手数料がかかるため、どれだけ得になるかは「金利差」と「手数料」のバランスで判断する必要があります。
2. 借り換えで発生する手数料とは?種類と概要
2-1. 借り換え時にかかる主な手数料一覧
住宅ローンの借り換えには、以下のようなさまざまな手数料や費用が発生します。
- 新しいローンに関する事務手数料
- 保証料
- 登記関連の費用(登録免許税・司法書士報酬など)
- 印紙税
- 団体信用生命保険料(金融機関による)
- 現在のローンの繰上返済手数料や解約違約金
これらの費用は一括で支払う必要があり、借り換えによるメリットが費用を上回るかどうかの判断が必要です。
2-2. 金融機関への手数料(事務手数料・保証料など)
新たなローンを契約する際に金融機関に支払う「事務手数料」は、定額型(3万円〜5万円程度)と定率型(借入額の2.2%など)があります。借入額が大きいほど定率型の手数料は高額になるため、コストに大きな差が生じます。定額型については金利が上乗せされるケースもあるので注意してください。
また、保証料は金融機関によって異なり、無料のところもあれば、数十万円かかることも。審査結果によって変わります。ネット銀行では保証料が不要なケースが多く、トータルコストを抑えたい人に人気があります。
2-3. 登記関連の費用(登録免許税・司法書士報酬)
住宅ローンを借り換える際には、旧ローンの「抵当権抹消登記」と新ローンの「抵当権設定登記」が必要です。これに伴って発生するのが登録免許税(借入額の0.4%が相場)と、登記手続きを代行する司法書士への報酬(5万円〜10万円程度)です。
2-4. 団体信用生命保険料の扱い
住宅ローン契約には通常、債務者に万が一のことがあった場合に残債が免除される団体信用生命保険(団信)への加入が義務付けられています。多くの金融機関では、団信の保険料は金利に含まれており、別途支払う必要はありません。ただし、がん保障や三大疾病保障などの特約付き団信を選ぶ場合は、金利上乗せや追加保険料が必要になることがあります。
2-5. 印紙税やその他の雑費も忘れずに
借り換え時に締結する金銭消費貸借契約書には、印紙税が課されます。借入額に応じて印紙税額が異なりますが、一般的には1〜2万円程度です。最近では大手銀行もネット完結型の住宅ローンを推奨しているため、その場合は印紙税はかからず費用を削減できます。また、書類の郵送費や交通費など、細かな費用も積み重なると数千円〜1万円程度になる場合があります。
3. 借り換えにかかる手数料の相場と具体例
3-1. 実際にいくらくらいかかる?金額の目安
住宅ローンの借り換えにかかる費用の総額は、以下が一般的な目安です。
- 事務手数料:3万円〜66万円(定率型の場合、借入額次第)
- 保証料:0円〜40万円程度
- 登記関連費用:10万~20万円程度
- 印紙税:1万円〜2万円
合計すると、50万円〜100万円程度のコストがかかることが多いです。ただし、金融機関や借入額によって大きく差が出ます。
3-2. 借入額別の手数料シミュレーション
例)借入額3,000万円のケース(定率2.2%の手数料)
- 事務手数料:66万円
- 保証料:0円(保証料不要の場合)
- 登記関連費用:20万円
- 印紙税:2万円
合計:約88万円
このように、手数料だけでも高額になることがありますので、金利による節約効果がそれ以上になるかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。
3-3. 手数料込みで借り換えは本当にお得?試算例付き解説
たとえば、残り25年・残高3,000万円のローンを金利2.0%から1.0%に借り換えた場合、総返済額は約300万円ほど削減されるケースがあります。そこから先ほどの手数料約88万円を差し引いても、実質210万円以上のメリットになります。逆に、残高が少ない、または残期間が短い場合は、手数料が節約額を上回る可能性が高いため注意が必要です。
4. 借り換えで得をするか損をするかの判断ポイント
4-1. 借り換えの損益分岐点を知ろう
借り換えのメリットが出やすい条件は以下の通りです:
- ローン残高が1,000万円以上
- 残りの返済期間が10年以上
- 借り換え前後の金利差が0.5%以上
これらの条件を満たしていれば、手数料を支払っても十分な節約効果が見込めます。
4-2. 手数料と金利差で比較する具体的な方法
借り換えによって浮く利息額と、借り換えにかかる諸費用を比較する「総支払額シミュレーション」が有効です。多くの金融機関や比較サイトでは、無料で使えるシミュレーターが提供されています。具体的な数字で判断することで、「なんとなく得しそう」ではなく、「確実に得になる」と確信を持って決断できます。
こちら三菱UFJ銀行のシミュレーションが使いやすいのでリンクを貼っておきます↓
住宅ローン借換シミュレーション | 三菱UFJ銀行
4-3. 借り換えに向いている人・向いていない人の特徴
借り換えに向いている人:
- 高金利でローンを組んだ人
- ローン残高・残期間が多い人
- 信用スコアが高く、審査に通りやすい人
借り換えに向いていない人:
- 既にローン残高が少ない
- 残り期間が短く、節約額が少ない
- 審査通過に不安がある(転職直後など)
5. 住宅ローンの手数料を抑える4つのコツ
5-1. 手数料が安い金融機関を選ぶ
金融機関によって、事務手数料の設定に違いがあります。例えば、定額型(3万円〜5万円)の銀行を選べば、定率型に比べて大幅にコストを抑えられます(定額型の場合は金利上乗せの可能性もあり)。キャンペーン中の銀行を狙うのもおすすめです。
5-2. 保証料が不要なプランを選ぶ
ネット銀行などでは、保証会社を介さないことで保証料が不要なローン商品が提供されています。これにより、数十万円の費用が削減できる場合があります。
5-3. ネット銀行で借り換えるメリット
ネット銀行は、店舗維持費がかからない分、金利が低く、手数料も割安な商品が多いです。また、スマートフォンだけで手続きが完結できる手軽さも魅力です。忙しい方や手数料を抑えたい方に向いています。
5-4. 司法書士費用を比較して節約する
登記手続きを金融機関任せにすると、提携先の司法書士を指定され、相場より高めの料金になることがあります。自分で司法書士を手配できる場合は、数社から見積もりを取り、比較することで費用を抑えられる可能性があります。
6. 借り換えにおすすめの銀行・金融機関
6-1. 手数料が安い&金利が低い銀行の特徴
- 保証料が不要
- 団信込みで追加費用がかからない
このような条件を満たす金融機関は、借り換えにおいて「総支払額」で見るとお得な場合が多いです。
6-2. 人気の銀行
SBI新生銀行:金利が低く、手続きもネットで完結。少しでも返済額を抑えたい方におすすめ
SBIマネープラザ:3大疾病50%団信が無料で付帯!金利も低く、対面でのサポートも充実。
三菱UFJ銀行:金利の低さは業界トップ。メガバンクの安心感もあり。
6-3. 金利だけで選ばない!総コストで比較しよう
金利だけを見ると魅力的でも、手数料が高いとトータルでは損になるケースがあります。借り換えを検討する際は、「金利+手数料=総返済額」で比較するのが賢明です。
7. まとめ:手数料を正しく把握して、住宅ローン借り換えで賢く節約しよう
住宅ローンの借り換えは、条件によっては数百万円の節約につながる有効な手段です。ただし、その一方で高額な手数料が発生することもあり、しっかりと事前に把握しておくことが重要です。金利差だけで判断せず、諸費用を含めた「総支払額」で本当にお得になるかを見極めましょう。借り換えに成功すれば、家計の大きな助けになります。