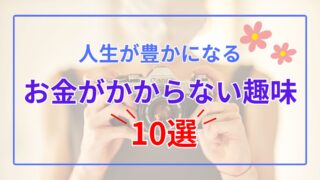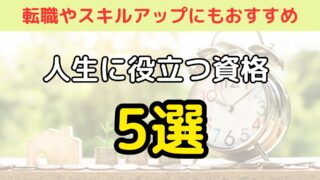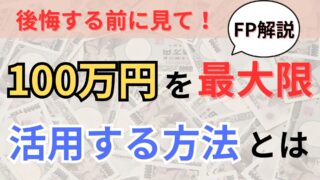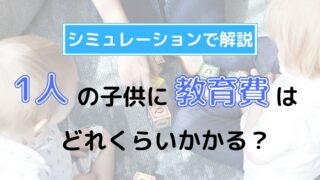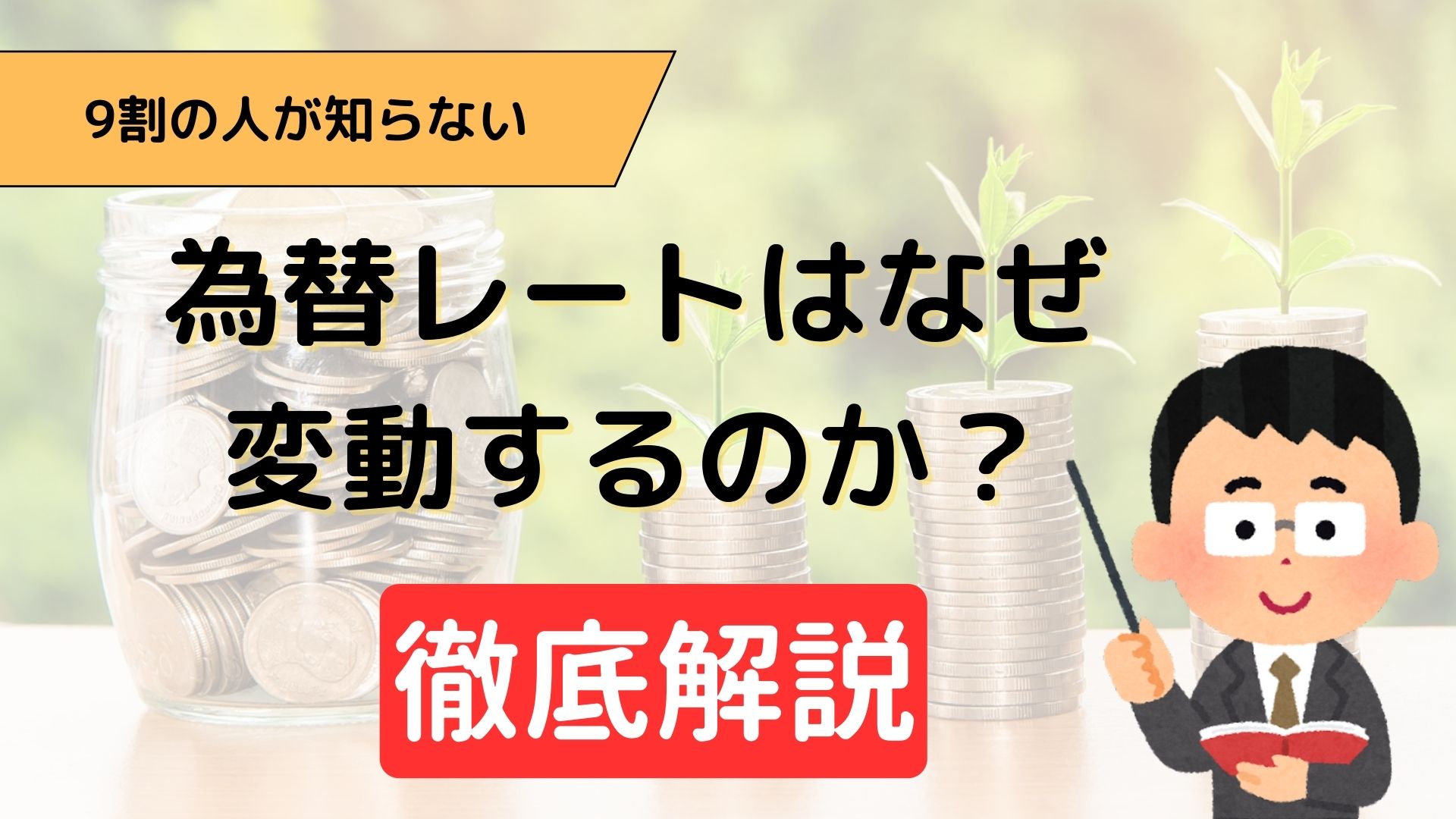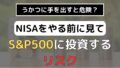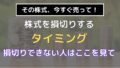為替相場は「眠らない市場」と呼ばれ、24時間休むことなく変動しています。
海外に旅行や仕事で行った際に、現地の通貨に両替をした経験はないでしょうか。
その際に、通貨を交換するための基準となるものが「為替レート」です。1ドル=○○円という形で表されます。
為替レートにセットで付いてくるキーワードとして「円安・円高」がありますが、例えば1ドル=100円から1ドル=110円になった場合は「円安になった」といいます。100円から110円なので直観的に円高と思いそうですが、「1円の価値が下がった」ので円安と覚えましょう。
また、為替レートに大きく関係するのは海外の資産に投資をしている方です。今ではつみたてNISAで米国のS&P500やオールカントリーなどに投資をしている方が増えてきていますが、これらの資産の増減には為替レートが大きく関わっています。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
この常に動き続けている為替レートですが、変動する要因は様々です。一言で表すとすれば「需要と供給のバランス」で変動します。
例として、アメリカへの旅行客が増える→ドルに両替する人が増える=ドルの需要が高まる→ドル高(円安)になるという流れです。
このように為替レートが動く要因は数多くありますが、その中でも影響力が大きく中長期的な変動を促すとされている3つの要因を解説します。
1. 両国の金利差
この金利差による為替レートの変動は「金利平価説」と呼ばれており、変動の大きな要因です。
今の日本では普通預金の金利が多くの金融機関で0.2%です。これは100万円を1年間銀行に預けておくと1,000円の金利が付くということです。銀行の金利はほとんど付かないというイメージがありますよね。
そんな中、アメリカの金利が3%や4%だったらどうでしょうか。同じ100万円でもアメリカでは3万、4万の金利を得ることができるという訳です。
この場合は、通貨を円からドルに変えてアメリカの金利で運用する人が増えます。ドルの需要が増えるため、ドル高円安へと動きます。
2. 物価の変動
物価の変動も為替レートに影響します。これは主に輸入や輸出に関係します。
企業は商品の材料などを国内や国外から仕入れています。例えば、国産のお肉を提供する日本の焼き肉店を例にします。
もし日本で鳥インフルエンザが流行し、鶏肉の価格が高騰したとします。そうするとコストがかさんで利益が圧迫されるので、より安いお肉を探します。
そこでアメリカのお肉がコスト面でメリットがあるとすると、アメリカのお肉を輸入して提供するようになるかもしれません。
その場合、アメリカのお肉はドルで支払わなければいけないので、ドルの需要が高まることになります。つまり円安ドル高に進むわけです。
この例のように、インフレが起きている国の方が通貨安になる傾向があります。
日本の物価が安い時は海外からの旅行客や、日本からの輸入が増え円の需要が高まることで円高ドル安になります。
3. 貿易収支
貿易収支は、(日本からの輸出額)-(日本の輸入額)で求められます。
貿易収支が黒字、つまり日本からの輸出が輸入を上回っている場合は円高になります。日本が海外に輸出をした際は、その代金として他国の通貨から円に交換して支払われるからです。円の需要が高まるということです。
逆に貿易赤字=輸入が輸出を上回っている場合は円安に向かっていきます。
先ほどの鶏肉の例のように1つの企業単体で見ると為替レートへの影響は小さいですが、このように国全体の輸出や輸入になると為替レートへの影響は大きくなります。
まとめ
今回は、為替レートが変動する要因を解説しました。要因は以下の3つです。
- 両国の金利差
- 物価の変動
- 貿易収支
これらの要因が絡み合って日々の為替レートは変動しています。
特に金利を調整している日本銀行の金融政策決定会合の内容は、為替レートに大きく影響を及ぼすのでチャックしてみましょう。
ご覧いただきありがとうございました。