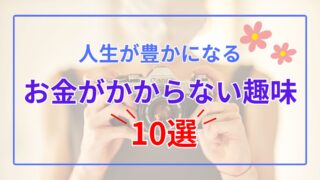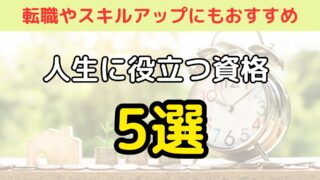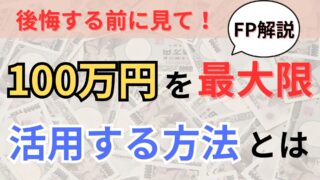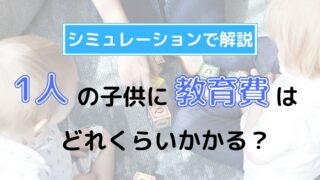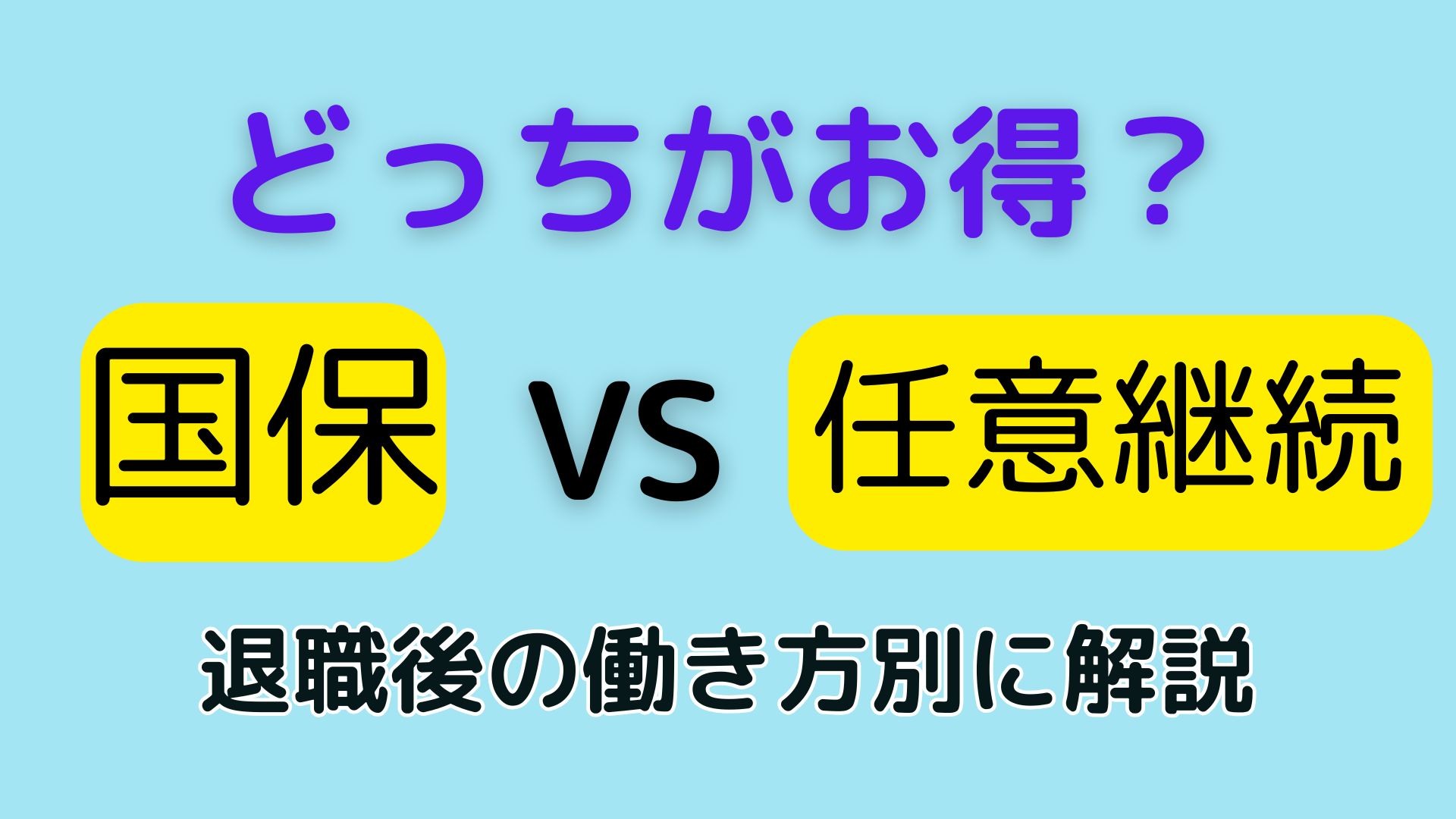会社を退職した後、必ず考えなければならないのが「健康保険をどうするか」という問題です。退職後にすぐ転職先で健康保険に入る方以外は選択肢は次の3つのみです。
最も保険料が安く済むのは家族の扶養に入る方法です。ただし、家族には迷惑をかけたくない、家族からの援助は期待できないという方も多いと思います。私自身も退職して自営業に切り替わりましたが、社会人として家族に心配をかけたくないと思い、扶養には入りませんでした。
この記事では、「任意継続健康保険」か「国民健康保険」のどちらかを悩んでいる方向けに、それぞれの保険制度の違いやメリット・デメリット、実際の保険料の比較、そして退職後の仕事のスタイルに応じた最適な選択を解説します。
1. 任意継続健康保険とは?
任意継続健康保険とは、会社を退職した後も、最長で2年間、会社員時代に加入していた健康保険(協会けんぽなど)を継続できる制度です。
任意継続の条件
- 健康保険に2ヶ月以上加入していたこと(会社に2カ月以上勤めていた)
- 退職後20日以内に申請すること
保険料のポイント
会社負担分がなくなるため、保険料は2倍になる
任意継続保険に加入する場合の保険料は簡単に確認できます。退職前の給与明細で「健康保険料」の額を見てください。在職中は会社が半分を負担してくれていますが、任意継続の場合は全額自己負担となるためその2倍の金額が毎月の保険料になります。
保険料は2年間一定
任意継続保険の保険料は原則2年間変わりません。次に解説する国民健康保険の保険料は前年度の所得金額に応じて毎年変動します。場合によっては退職後、最初の1年間は任意継続保険に入って、2年目は国民健康保険に入った方が保険料が安くなるという方も多いと思います。その点も含めて比較検討する必要があります。
保険料の上限が決まっている
任意継続保険の保険料には上限が設定されているため、退職前の年収が高かった人にとっては割安になることもあります。
2. 国民健康保険とは?
国民健康保険(国保)は、主に自営業やフリーランス、無職の人が加入する保険制度です。市区町村が運営しています。
国保の保険料の特徴
前年の所得に応じて保険料が決まる
国民健康保険の保険料は前年度の所得に応じて保険料が決まります。会社を辞めて転職や独立をした方で収入が大きく減ってしまった方は前年度の高い収入で保険料が計算されてしまうので負担感がかなり大きくなってしまいます。
世帯の人数や地域によって大きく異なる
国民健康保険料は世帯の中で加入している人数や年齢などによって計算されます。具体的には「所得割」「均等割」「平等割」の3つを合計したものが支払う保険料になります。また、国民健康保険は市区町村が運営しており、地域によって保険料は異なります。
正確な保険料は各市区町村のホームページでシミュレーションができますので、そちらでご確認ください。勤めていた会社の源泉徴収票が手元にあるとシミュレーションがやりやすいです。やり方が分からない方はお近くの役所にある国民年金課で確認してもらうといいでしょう。
退職後に所得が大きく減る場合は保険料も安くなる
会社の退職後に大きく収入が減ってしまった場合などに国民年金保険料を減免してもらえる制度が市区町村によってあります。例えば、所得が一定以下に減った場合は保険料の2割~7割が減免になったり、前年度比で30%以上減少した場合に所得割額の10%~100%が減免になるといった制度があります。
こちらも市区町村によって制度内容や基準が異なりますので、ご自身の市区町村にて確認してみてください。
3. 退職後の働き方パターン別のおすすめ保険
パターン1:しばらく無職・失業保険を受給予定
→ 任意継続保険がおすすめ
理由:前年の収入が高く、国保は高くなりやすいです。任意継続の方が保険料が安く抑えられるケースが多い。
パターン2:フリーランスとして独立
→ 国民健康保険がおすすめ
理由:初年度は高めですが、翌年以降、所得が減ると保険料も下がります。扶養の概念がなく、家族がいても全員加入できます。
また、手間はかかりますが、初年度は任意継続に入り、2年目以降に国保へ切り替える方法もおすすめです。2022年の法改正により任意継続保険の途中脱退ができるようになりました。1年目は割安な任意継続保険に加入し、所得が減少した翌年(2年目)に国保へ切り替える方法がベストな方も多いです。
パターン3:すぐに再就職(1〜3ヶ月以内)
→ 任意継続でも国保でもどちらでもOK
短期間なら保険料の差は大きくなく、任意継続にしておけば再就職後もスムーズです。ただし、再就職先で健康保険に入ったら即切り替えが必要になります。
パターン4:家族の扶養に入れる場合(配偶者が会社員)
→ 配偶者の健康保険の扶養に入るのがベスト
所得が一定以下で条件を満たす場合、保険料の自己負担がゼロになります。家族が手助けしてくれる方は扶養に入った方がいいでしょう。
4. 注意点・補足事項
- 任意継続は2年間で自動終了し、その後は国保に入る必要があります。
- 国民健康保険は自治体によって金額が大きく違うため、必ず自分の住んでいる市区町村の情報を確認しましょう。
- 退職後の20日以内に手続きしないと任意継続は利用できません。
まとめ:どちらが良いかは「今後の働き方」と「前年の年収」で決まる
| 状況 | おすすめの保険 |
|---|---|
| 前年の収入が高い・無職予定 | 任意継続 |
| 収入が減る見込み・独立予定 | 国民健康保険(1年目のみ任意継続もあり) |
| 家族の扶養に入れる | 扶養が最も有利 |
| すぐに再就職する予定 | どちらでもOK |
保険料は1年間で数万円〜十数万円の差になることもあるため、自分の状況をよく整理してから判断しましょう。