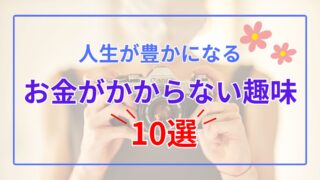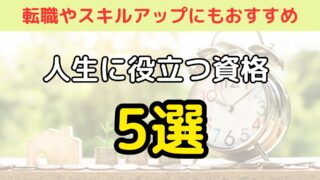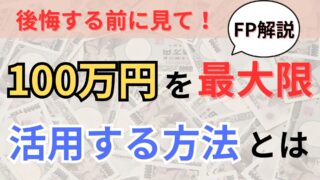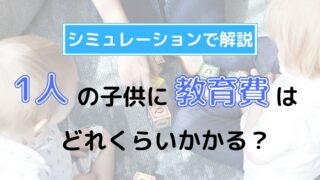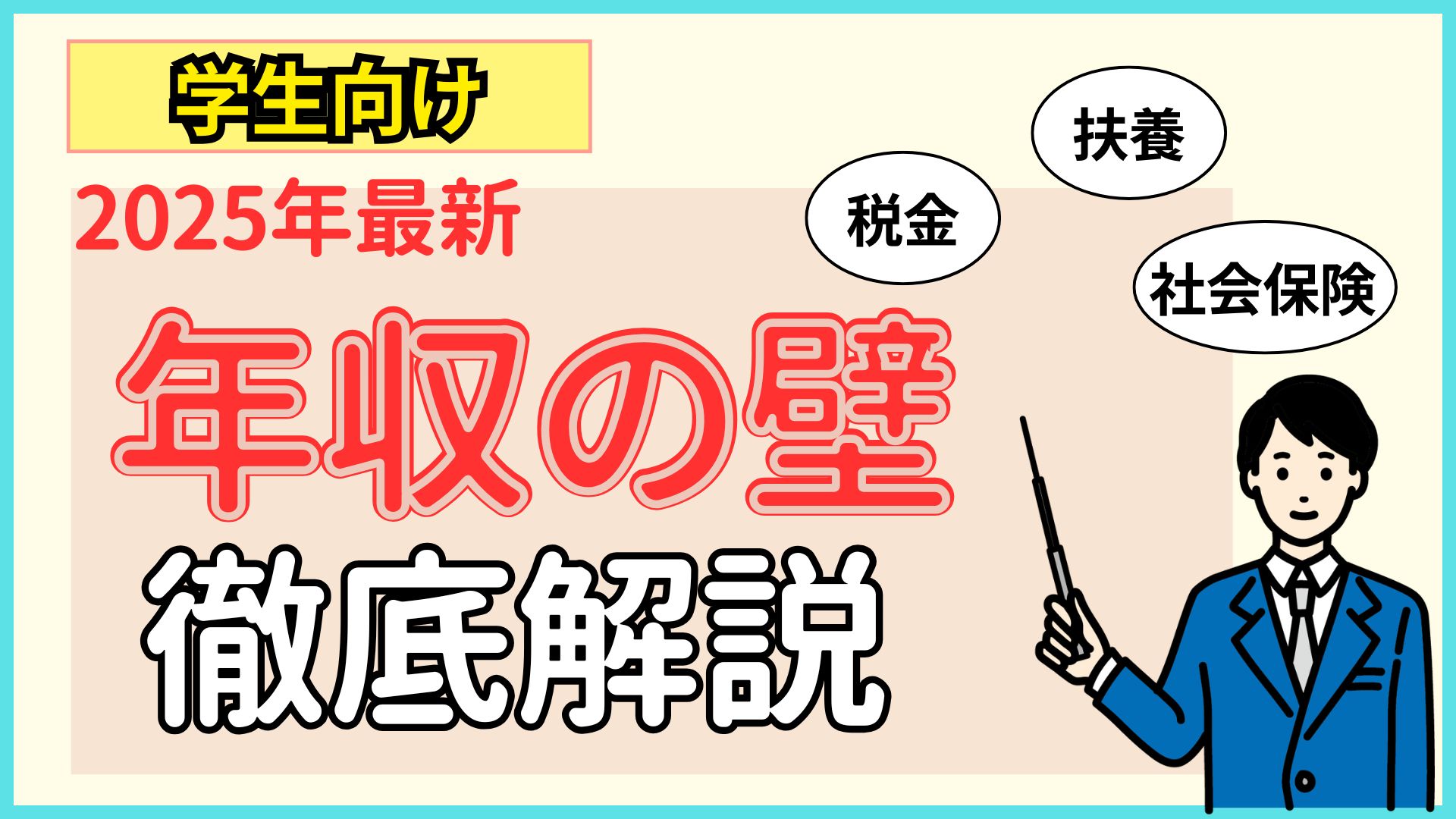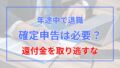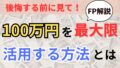所得税や住民税、社会保険に関わる「年収の壁」。2025年度から制度が大きく改訂され、この年収の壁が引き上げられることとなりました。
学生の方でアルバイトをしている方にとっても、一定水準を超えると税金が引かれたり親の扶養から外れたりと気を付けるべき点がいくつもあります。
この記事では学生目線での年収の壁を金額ごとに解説し、自分はいくらまで働いていいのかが分かるよう説明していきます。
そもそも年収の壁というものがあまり分かっていない方はこちらの記事をご覧ください。年収の壁の種類などから解説していますので、年収の壁の全体像が分かります。
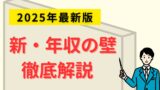
大学生の「年収の壁」全体像
大学生にとっての年収の壁は大きく以下の4つに分けられます。
| 年収110万円超 | 住民税が発生 |
| 年収130万円超 | 親の扶養(社会保険)から外れる |
| (年収134万円超) | (勤労学生控除を使っても)住民税が発生 |
| 年収150万円超 | 親の所得税が増える |
| 年収160万円超 | 本人に所得税がかかる |
これからそれぞれの年収の壁について詳しく解説していきます。特に注意して確認していただきたい点は「本人の所得に影響するか」「親の所得に影響するか」です。それぞれが別々の意味合いを持っており金額もばらばらになるので、複雑ですが整理しながら確認いただければと思います。
110万円の壁:住民税が発生
年収110万円を超えると本人に住民税が発生
自分の所得に対して発生する税金は所得税と住民税の2つがあり、それぞれ基準となる年収が異なります。住民税は市区町村に納める税金であり、若干異なる場合もありますがほとんどの市区町村で110万円が住民税発生の基準になります。
住民税は働いている学生本人にかかる税金になるので親の所得には影響しません。ただし、奨学金の貸与を受けている場合などで住民税非課税の条件が付いていることがあります。その場合は住民税が発生する年収を超えないようにしなければいけません。
尚、住民税は前年度の所得を元に計算されるため、今年(1月~12月)働いた分の住民税は翌年に請求される点も注意しましょう。
勤労学生控除を使えば年収134万円まで住民税非課税
年収110万円は学生でない社会人にも共通する年収の壁でしたが、学生の方は手続きすることで住民税の年収の壁を引き上げることができます。それが「勤労学生控除」という制度です。これは年収150万円までの学生が申し込める制度で、所得から一定の金額が控除されます。これにより、学生の方は年収134万円までであれば住民税がかからないということになります。
ただし、この制度を利用するには勤め先で年末調整をしたり、ご自身で確定申告をしないといけないため注意をしましょう。
130万円の壁
続いては130万円の壁です。こちらは社会保障上の壁と言われ、健康保険などの社会保険に関わる年収の壁です。学生の方は基本的に親の扶養に入っている方が多いと思います。保険証に親の勤務先や親の名前が入っている方はその方です。親の扶養に入ることで、親に負担がかかることなく、自分自身も健康保険に入ることができるというメリットがありました。
しかし、学生であっても年収130万円を超えてしまうと親の扶養から強制的に外れてしまうんです。また、年収130万円といっても月単位で計算されるケースもあります。例えば扶養から外れる条件として
- 2カ月以上連続して月収が108,334円を超える(年収130万円を12で割った金額)
- 過去3カ月の月収平均が108,334円を超える
など、親の勤め先によって基準が異なっていますので月単位で年収が130万円を超えそうになったら必ず親に確認をしましょう。扶養から外れることで学生本人が国民健康保険に加入するか、勤め先で社会保険に加入することになります。そうなると、手取り額が大きく減ってしまうことになり、「そんなはずじゃなかった」ということにもなりかねません。
例えば、130万円を超えてアルバイト先の社会保険に加入すると手取り額への影響はこのようになります。(ざっくりした計算です)
このように、130万円を超えると手取り額で10万円以上の差が出てしまいます。少しでも稼ぎたい学生の方にとっては大きな痛手にもなりかねないので十分注意をしてください。
尚もう一つ注意すべき点は、この130万円には交通費や残業代などの手当ても含まれるということです。働いた時間で月給を計算しないように注意をしましょう。
150万円の壁
続いては150万円の壁ですが、こちらは親の手取りに影響する年収の壁になります。親は通常、子供を養っているという名目で一定額を「特定扶養控除」「特定親族特別控除」として税金の軽減を受けることができます。
この「特定扶養控除」「特定親族特別控除」の基準額が2025年から大きく引き上げられました。改正後の基準は
- 年収123万円までは「特定扶養控除」で63万円控除
- 年収123万円~150万円までは「特定親族特別控除」で63万円控除
- 年収150万円を超えると「特定親族特別控除」が段階的に減少→年収188万円で消滅
尚、上記の金額は19歳~22歳の子供を前提にしています。16~18歳の子供は別の基準が設けられていますので注意して下さい。
つまり、年収150万円までは親の控除に影響はありませんが、150万円を超えると徐々に親の手取りが減ってしまうということです。ただし、控除額は段階的に減少していく仕組みになっているため、急激に手取りが減るということではありません。188万円を超えた時点で「特定親族特別控除」は0になります。
160万円の壁
最後の年収の壁は160万円の壁です。これは働いている学生本人に所得税が発生する基準になります。所得税というのは基本的に自分の収入から「給与所得控除」や「基礎控除」を除いた部分に対して税率がかけられ決定します。
2025年度からの改正で給与所得控除が65万円に、基礎控除額が95万円に引き上げられたことで合計の160万円が所得税の壁ということになりました。
学生アルバイトで年収160万円以上稼ぐケースは少ないかもしれませんが、こちらも注意をしましょう。
自分が目安にするべき年収は?
ここまで様々な年収の壁を紹介してきましたが、結局自分がどこまで働いたらいいか分からないという方もいるかと思います。そんな方のためにいくつかのポイントに絞りましたので参考にしてください。
基準①:住民税の110万円の壁
学生でない社会人の方は住民税の壁を意識することはあまりないかもしれませんが、学生にとっては需要な基準になる可能性があります。それは、奨学金や給付金などを受けている方にとって住民税非課税というものが条件になっている可能性があるからです。今受けている奨学金などの条件を必ず確認しておきましょう。住民税の壁を越えて働き、奨学金が停止ということになれば逆に生活が圧迫してしまうかもしれません。
また、住民税は市区町村によって110万円でない可能性もあるため、正確な情報はそれぞれの市区町村に確認をしてください。
基準②:親の扶養から外れる130万円の壁
年収130万円を超えると親の扶養から外れ、勤め先で社会保険に入ったり、自ら国民健康保険に加入する必要が出てきます。そうなると、自分の手取り額が大きく減少してしまう可能性があります。
親の扶養で居続けたい方は年収を130万円までに抑えましょう。尚、この年収130万円には交通費や残業代など全て含まれますのでその点も注意して下さい。
まとめ
今回は、2025年に改訂された年収の壁について学生の方向けに解説を行いました。様々な種類の年収の壁があり、複雑かと思いますがそれぞれ金額別に整理してみてください。年収の壁は自分の収入だけでなく、親の手取りにも影響する重要な基準になりますので、しっかり確認をした上で働く時間を設定しましょう。