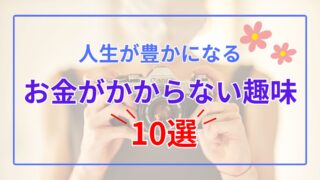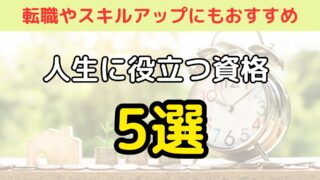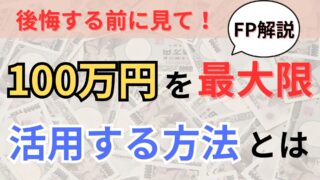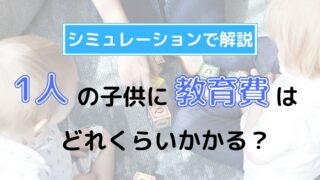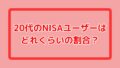最近ニュースで「プラチナNISAができる」という報道を見ました。これは高齢者のためのNISA制度で岸田前首相が会長を務めている資産運用立国議員連盟により提言され2026年の税制改正に向けて動き始めているということです。
このプラチナNISAとはいったいどういうものなのでしょうか。現行のNISAとの違いやプラチナNISAで高齢者の投資行動がどう変わるのか、気を付けるべき注意点なども解説します。
プラチナNISAの概要
プラチナNISAは65歳以上の年金生活者層に限定し、従来のNISAでは購入できない毎月分配型の投資信託も買えるようにするそうです。
その背景として2024年にNISAが制度改定された際、毎月分配型の商品は長期的な資産形成に向いていないとされNISAの対象商品から除外されました。毎月分配型の商品は毎月安定した分配金を受け取れるのがメリットではありますが、投資信託が生み出している利益以上に分配金が支払われることもあり、そうすると支払った元本がただ戻ってきてしまうだけになるのです。長期的に大きな資産を作りたい方にとっては出た利益を再投資していった方が効果的なので毎月分配型の投資信託はNISAから外れました。
対して毎月分配型の商品は高齢者にとってメリットがあると言えます。例えば退職金など、まとまったお金を毎月分配型の商品に投資することで資産を運用しながら少しずつ取り崩していくことができます。毎月の分配金が安定している投資信託を選べば、年金と同じように月々の収入を安定させることができます。また、毎月の分配金に対しても税金がかからないのでプラチナNISAのメリットです。
プラチナNISAはいつから?
プラチナNISAは2026年の税制改正に向けて動き始めているというニュースが出ています。まだ構想段階に過ぎないのではっきりとした時期は決まっていませんが、予定通り2026年の税制改正に間に合えば2027年から実際に稼働していくのではないでしょうか。
退職金の運用などを検討している方は今からでも情報収集などの準備をしておきましょう。
プラチナNISAのデメリットは?
長期投資には不向き
プラチナNISAで投資が可能になる毎月分配型の商品は、安定した分配金を目標にしているため投資信託が出している利益以上に分配金が支払われることがあります。この利益以上に払われる分配金は「元本払戻金」と言われ自分が投資した元本が戻ってきているだけとなります。つまり、運用益を出し続けられなければ投資元本がどんどん減っていってしまうというわけです。その意味では10年以上の長期的な投資としては毎月分配型の商品はデメリットになってしまいます。
非課税のメリットが享受しにくい
投資信託の分配金は運用益が出ていればそれに対し税金が発生するのでNISAで運用するメリットはあります。しかし、元本払戻金については非課税の適用がありません。仮に毎月ほとんどが元本払戻金によって手元に戻ってくるとするとほとんどNISAによる非課税のメリットを受けずに元本が減っていくことになります。このように毎月分配型の商品は非課税のメリットが受けにくいというデメリットもあります。
プラチナNISAの限度額は?
プラチナNISAの限度額についてはまだ公表されていません。現行のNISAは成長投資枠240万、つみたて投資枠120万となっていますがこれとは別の枠で設定される可能性が高いでしょう。
退職金などを一括で運用したいニーズも高いと思いますので現行に比べ高めの限度額が設定されるのではないでしょうか。
相続税対策にはなるか
原則、NISA口座を保有している人が死亡した場合、その時点で非課税口座ではなく課税口座へと移行してしまいます。タンス預金をしておくより運用してより多くの資産を残せる可能性はありますが、相続税の軽減対策にはなりませんので注意をしましょう。