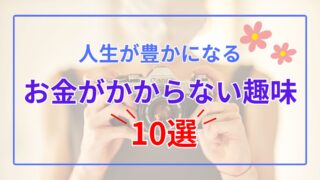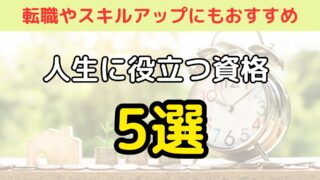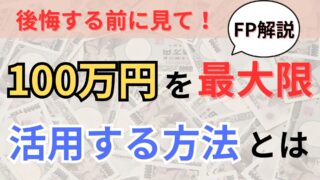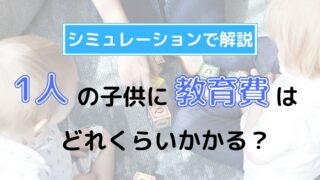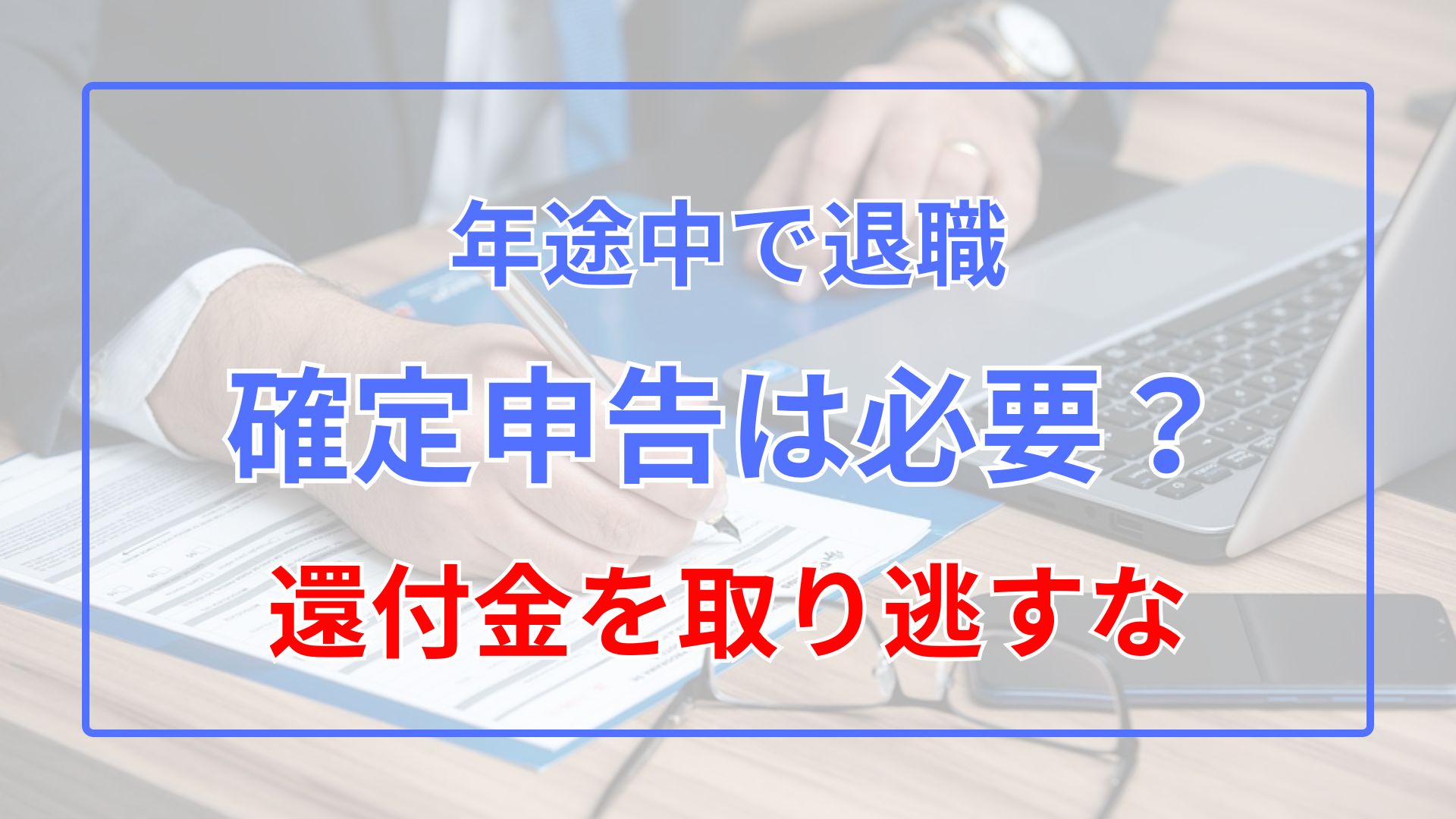会社員として働いていると、年末に勤務先が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする機会は少ないかもしれません。しかし、年の途中で退職した場合は話が変わってきます。特に、再就職をしていない場合や、年末調整がされていないまま退職した場合は、自分で確定申告を行わなければ、本来受け取れるはずの還付金を受け取れない可能性があります。
退職後に確定申告が必要になるケースもあれば、申告義務はないけれど申告することで税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。どちらにせよ、正しく理解して行動することが、無駄な税金を払わずに済む第一歩となります。
この記事では、確定申告の基礎と、なぜ年途中の退職者が申告を検討すべきなのかについて解説します。難しそうに思える手続きも、ポイントを押さえておけば意外と簡単です。
1. 年の途中で退職したら確定申告は必要?
1-1. そもそも「確定申告」とは?
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得とそれに対する税金を自分で計算し、税務署に申告する手続きです。払い過ぎた税金が戻ってくる「還付申告」や、逆に足りなかった分を納める「納付申告」などがあります。
会社員の場合は勤務先が年末調整を行うことで、この手続きを代行してくれます。しかし、退職していると年末調整を受けられないため、自分で確定申告をする必要が出てきます。
なお、フリーランスや個人事業主は毎年確定申告が必要ですが、会社員であっても副業収入がある場合や、株取引や仮想通貨取引による所得がある場合など、例外的に申告義務が生じることもあります。確定申告は「会社員には関係ない」と思い込まず、自分の収入や支出を振り返って判断することが重要です。
1-2. 年末調整されていない人は要注意
退職した時期によっては、その年の年末調整を受けられません。年末調整を受けずにそのままにしておくと、本来受けられる控除(扶養控除、生命保険料控除、など)が反映されず、税金を払い過ぎたままになっている可能性があります。
このような場合は、確定申告を行うことで税金の還付が受けられる可能性が高いため、忘れずに対応しましょう。実際に、「自分は退職して収入が少なかったのに、こんなに税金を払っていたのか」と驚く人も多く、確定申告をすることで数万円〜十万円単位の還付を受け取れるケースもあります。
特に、医療費が多くかかった年や、引っ越し・転居にともなう費用、保険料の支払いが増えた年などは、控除対象が増える傾向があるため、申告すればするほど得をする可能性もあるのです。また、2024年には定額減税が行われていたため、それを受けずに退職した方などは2025年の確定申告で還付が受けられる可能性が高いです。
2. 年途中で退職した人が確定申告すべき具体的なケースとは?
年の途中で退職した場合、自分が確定申告をするべきなのか、迷う人は多いです。ここでは、よくある退職後のパターンごとに、確定申告が必要かどうか、また申告することで得られるメリットについて詳しく解説します。
2-1. 年末調整を受けていない場合
会社を退職して年末調整を受けていない場合、確定申告が必要です。所得税の精算がされていない状態なので、源泉徴収されていた税金の一部が戻ってくる(還付)可能性があります。
※ただし、再就職先で年末調整を受けられた方は確定申告は不要です。
年末調整では、年間の給与収入をもとに所得税の過不足を調整します。退職時にはその年の収入が確定していないため、税金はあくまで「仮の計算」で引かれています。そのため、年末調整が行われていないと、本来なら受けられるはずの控除(扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など)が考慮されておらず、税金を多く払っている可能性があるのです。
退職時にもらえる源泉徴収票には、支払金額や控除額、天引きされた税金の情報が記載されています。これを元に確定申告を行えば、余分に払った税金を取り戻せます。
2-2. 退職後に再就職せず、収入がなかった場合
退職後に再就職せず、他に収入がなかった場合でも、源泉徴収されていた税金があれば還付を受けられる可能性があります。特に退職時期が早かった人や、年間の収入が少ない人は還付額が大きくなることがあります。
この場合、申告義務はない「任意の申告(還付申告)」となります。義務はありませんが、申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があるため、ぜひ申告を検討しましょう。しかも、還付申告は5年間さかのぼって申請が可能です。
たとえば、年間の収入(給与所得)が160万円以下だった場合(2025年以降)、そもそも課税対象ではないため、源泉徴収されていた所得税はすべて戻ってくる可能性があります。これは「所得税が非課税になる基準(基礎控除と給与所得控除の合計)」を下回るためです。
2-3. 退職後にアルバイトや副業など別の収入があった場合
退職後にアルバイトや副業を行っていた場合、複数の収入を合算して確定申告を行う必要があります。副業などで年間20万円を超える所得がある場合は申告義務が発生します。
たとえば、前職の会社から給与収入が50万円あり、退職後にアルバイトで年間30万円の収入があった場合、それぞれの収入を合算して課税対象となるため、確定申告が必要になります。副業がフリーランス(業務委託)だった場合は、収入から経費を差し引いた「所得」が20万円を超えるかどうかが基準になります。
「収入」=売上、「所得」=売上−経費、と覚えておくとわかりやすいです。
2-4. 医療費が高額だった・保険料を多く支払った場合
年間の医療費が10万円以上かかった場合や、退職後に自分で国民健康保険や国民年金を支払っていた場合は、確定申告で控除を受けられます。申告によって税金の一部が還付される可能性があります。
特に、家族の医療費も合算できる点は見逃せません。医療費控除では、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含めて計算できます。また、医療費控除の対象には通院の交通費や、治療にかかった薬代、入院費用なども含まれます。
保険料控除についても、退職後に一括で支払った国民年金や国民健康保険の保険料は、全額が控除対象となり、所得税の軽減につながります。
3. 確定申告で利用できる主な控除項目
確定申告では、さまざまな「控除」を活用することで、所得税や住民税の負担を減らすことができます。ここでは、退職後の申告でよく使われる主な控除項目について詳しく解説します。
3-1. 社会保険料控除
退職後に自分で国民健康保険や国民年金を支払った場合、その支払った保険料は全額が控除対象です。納付額が大きい人ほど、税金の軽減効果も高まります。
3-2. 生命保険料控除・地震保険料控除
退職後も生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合、それらも控除の対象になります。年間支払額に応じて、最大で数万円~10万円強の控除が可能です。
3-3. 医療費控除
前述のとおり、1年間で支払った医療費が10万円を超える場合(もしくは所得の5%を超える場合)には、医療費控除が利用できます。領収書やレシートを保管しておくことが重要です。
3-4. 前年に定額減税などの減税施策が行われた
こちらは例年のものではありませんが、前の年に減税施策が行われていた場合はその分が確定申告で還付される可能性があります。直近で2024年に定額減税が行われているので、2025年に確定申告をしていない方は還付が受けられる可能性があります。
4. 確定申告で受けられる還付金の目安
「確定申告をして、どのくらいお金が戻ってくるのか?」というのは、多くの人が気になるポイントです。実際の還付額は、収入・控除の内容・税率によって異なりますが、ここではいくつかの事例を紹介します。
4-1. 年収200万円で4月退職・その後無収入だったケース
・給与収入:80万円 ・源泉徴収税額:3万円 ・社会保険料控除:12万円
課税所得はゼロになるため、3万円の源泉徴収税額は全額還付される可能性が高いです。
4-2. 年収300万円で10月退職・年末に再就職したケース
・給与収入:250万円(前職)+50万円(新職) ・年末調整なし ・生命保険料控除:5万円 ・社会保険料控除:30万円
年末調整を受けていないため、年収の合算により過剰に税が徴収されている可能性があります。控除と合わせて申告することで、5〜10万円程度の還付が受けられる可能性があります。
5. 確定申告の手続き方法と必要書類
申告の方法には大きく分けて「紙の書類で申告」「e-Taxでオンライン申告」の2つがあります。ここでは、それぞれの方法と必要書類について説明します。
5-1. 確定申告の提出時期
毎年2月16日〜3月15日が原則の申告期間です。ただし、還付申告だけであれば、退職した翌年1月から5年間の間でいつでも申告が可能です。
5-2. 必要書類一覧
- 源泉徴収票(退職時にもらったもの)
- 支払った保険料の控除証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- マイナンバー確認書類(個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
5-3. e-Taxを使うメリット
オンラインで手続きが完結するe-Taxは、手続きが早く、還付もスムーズです。マイナンバーカードを使ってスマホやPCから申請が可能で、書類の提出も一部省略できます。
6. まとめ:退職後は確定申告で損をしないようにしよう
年の途中で退職した場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けられるケースが多くあります。年末調整がされていない、再就職していない、他に収入があった、控除対象となる支出があった――こうした状況に心当たりがある方は、ぜひ申告を検討してください。
正しい知識をもって行動することで、本来取り戻せるお金を確実に受け取ることができます。面倒に感じるかもしれませんが、一度やってみると意外と簡単。この記事を参考に、確定申告の準備を進めていきましょう。