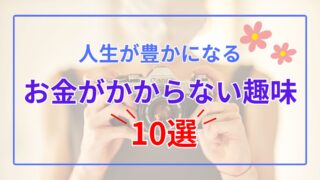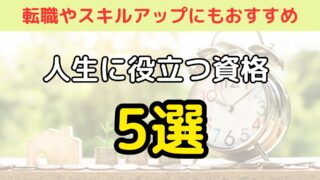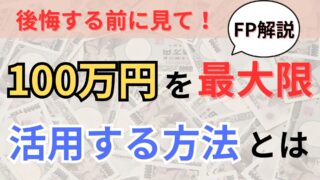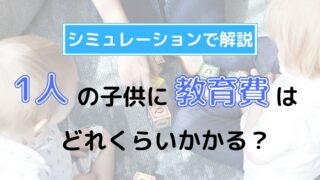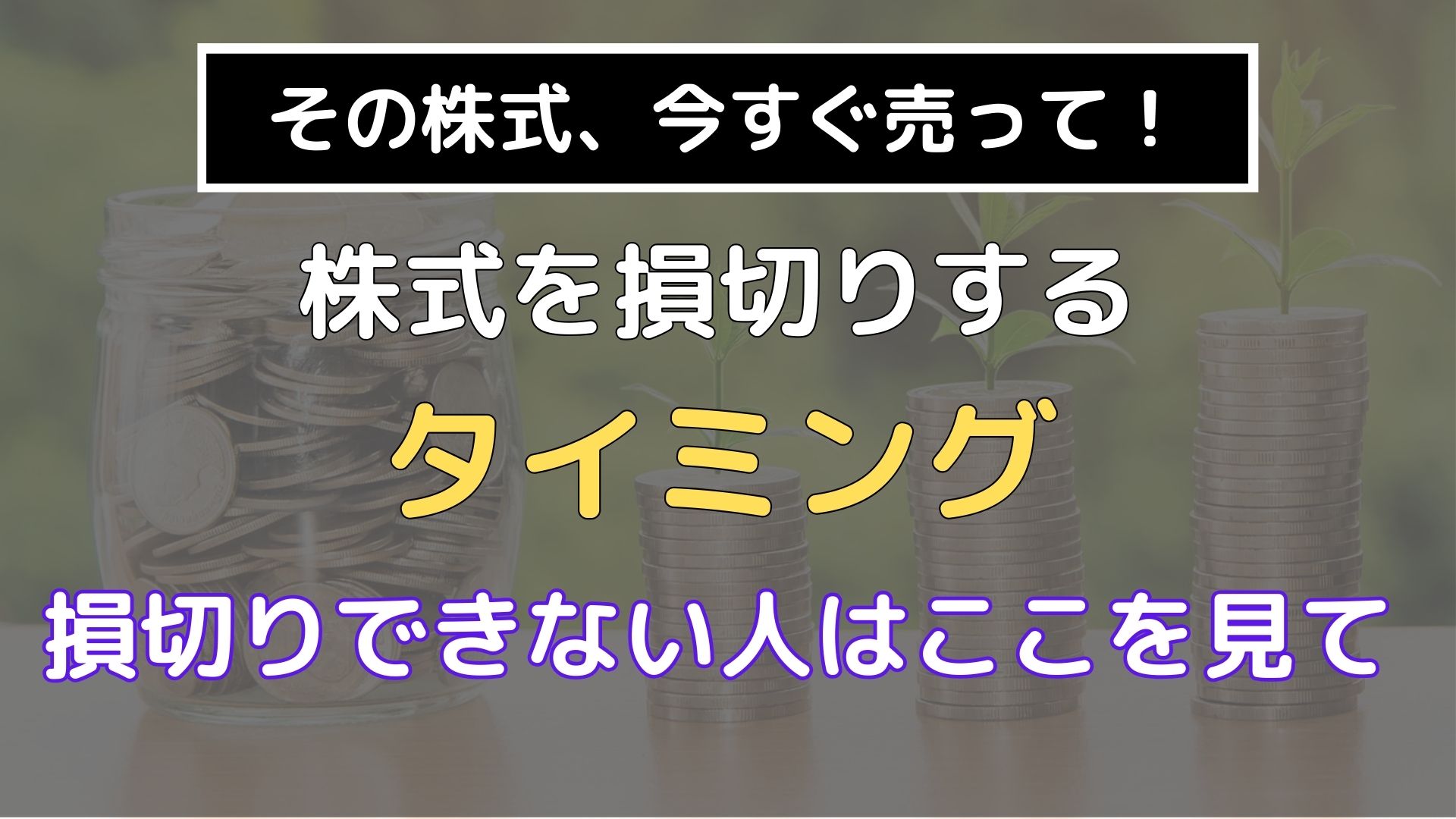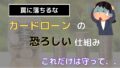「損切り」とは含み損を出している株式を売却して損失を確定させることです。
特に株式投資を始めたばかりの人は損切りをするタイミングが分からず、損失が大きく膨らんでしまうと、さらに損切りができなくなるという負の循環に陥ってしまうことがよくあります。
そうならないためにも、損切りのタイミングや取引のルールを自分の中で明確にしておくことは非常に重要です。
中には、値上がりの利益は求めておらず配当金や株主優待を目的として株式投資をしている方もいると思いますが、短期、中期的な値上がり益を求めて投資をしている方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
損切りが必要な理由
1. 損失の拡大を防ぐ
損切りのタイミングを逃してしまうと、自分の予想以上に株価が下落する可能性があります。
一度大きな含み損を出してしまうと、ますます損切りができなくなり株価が元に戻るまで数カ月~数年と待つことしかできない状態が続く場合もあります。
人の考え方として、「今は下がっているけど、すぐにまた戻るだろう」という根拠のない楽観思考をしてしまう傾向があります。まずはこの考え方を断ち切りましょう。
「業績が伸びているから」や「トレンドに乗っているから」など株価が上昇する根拠がある場合は、大丈夫ですが根拠のない場合は、損失が膨らむリスクが高くなります。
2. 自己資産の管理
もう一つは自己資産の管理です。
株式投資はそもそも食費や固定費などの生活費を除いた、余裕のある資金で行っていることが前提ですが、その中でもこの金額は最低限必要だという基準もあるでしょう。
例えば、急な出費が発生した際には株式を売却しなければいけない状況にもなるでしょう。そんな時に、大きな損失が出てしまっていては大変です。
株式はその企業が成長していれば長期的に上昇していきますので、短期的な下落は気にすることなく長い目で保有することができると思います。
しかし、短期的な投資を目的にしている場合は特に損切りの基準を設けておくことは重要です。
損切りをするタイミング:3つの基準
1. 損失率や損失額の設定
1つ目は、損失率や損失額のラインを決め、それを超えたら売却をするという手法です。
「購入時より○○%下落したら売却する」「損失額が○○万円を超えたら売却する」と決めておきます。
損失額を設定する上で注意すべきことは、それぞれの銘柄で下落の仕方が大きく異なるということです。例えば、株価が800円の銘柄が1日で100円以上下落することは滅多にないですが、株価が3万円の銘柄が1日で100円以上下落することはよくあります。
つまり、株価が違うとその上昇や下落幅も異なってくるということです。損失額で損切りの設定をする際は、銘柄ごとに決めることをおすすめします。
また、損失額や損失率でラインを決める場合は、「逆指値注文」を活用するのがおすすめです。
通常の「指値注文」では、「株価がここまで下がったら購入する」「株価がここまであがったら売却する」というように、なるべく安い価格で買いたい、なるべく高い価格で売りたいといった方が使う注文の仕方です。
対して「逆指値注文」とは「株価がここまで下がったら売却する」「株価がここまで上がったら購入する」という注文の仕方です。
この逆指値注文を活用することで、株価がこの価格を切ったら売却するという設定ができるので、損切りを自動的に行うことができます。
普段は仕事で株価の動きを追うことができない方などにおすすめの方法です。
また、先ほどもお伝えしたように、自分の資産全体としてこの金額を下回ることができないという基準から損切りのラインを決めることもおすすめです。
2. 決算など重要なイベントの前
企業の決算発表は株価が大きく動くイベントです。特にトヨタやソフトバンクなどの大型株になるとより注目度が高まり株価に影響を与えます。
このような注目が集まる発表などの前に損切りをすることも1つの方法です。
決算内容が市場予想を下回ったり、赤字に転じたりすると株価が大きく下落することがあります。場合によっては、売りの注文が集中してしまい、どんどん下がっているのに取引が成立しないということもあるかもしれません。
決算発表の他にも、例えば年に8回開催される日銀の金融政策決定会合では、金利の引き上げなどによって為替レートに影響が及ぶと、輸出企業の株価が大きく変動したりします。
このようなイベントの前に一度損切りをして様子を見ることも大きな下落を避けるための対策としては有効な手段です。
また、投資先企業だけでなく、関連企業や主要取引先などの決算発表も重要ですので発表日はスケジュールで管理をするようにしておきましょう。
3. 購入した根拠が崩れた時
個人が株を購入する根拠は様々あると思います。「業績が上向きで次の決算も増益が期待できるから」「テクニカル分析で移動平均線の原理から上昇傾向にあると判断した」「半導体のトレンドに沿って伸びていきそうだから」などが挙げられます。
そういった予測に沿って購入したのであれば、その前提が崩れた場合は損切りをするタイミングです。
例えば、移動平均線の考え方で購入したのであれば、下落傾向に転じた時には損切りをすべきです。
また、業績が上向きであると判断し購入したのであれば、業績の悪化などのニュースが出た際には損切りをすべきです。
このように、自分が購入の根拠となるものが崩れた際には迷わず損切りをしましょう。
損切りをする際の注意点
損切りにおいて最も大切なことは、「自分で決めたルールを厳守すること」です。
損切りのラインに到達した際に、「基準がもともと厳しかったからもう少し基準を緩めよう」「今回の下落は特殊だから例外的にもう少し保有しよう」とルールを変えてしまうことはよくありません。
そういったルールの変更を許してしまうと、次も同じことが繰り返されてしまい、ルールを守らない癖がついてしまいます。結果として、予想以上の損失が発生してしまうかもしれません。
購入前に決めた損切りルールは売却するまで必ず守るようにしましょう。
まとめ
今回は損切りをする際のルールについて具体的な方法を3つ紹介しました。
- 損失率や損失額の設定
- 決算など重要なイベントの前
- 購入した根拠が崩れた時
健全な株式投資を行う上で、損切りのラインを設定することは非常に重要です。
また、自分で定めた損切りルールを順守することも大切です。
ご覧いただきありがとうございました。