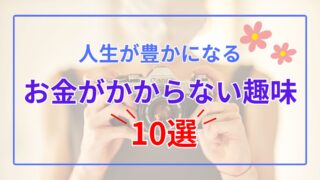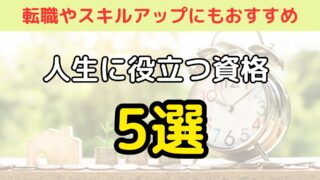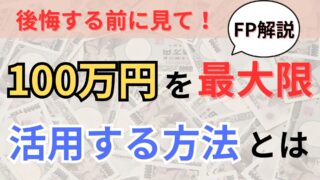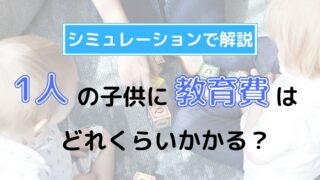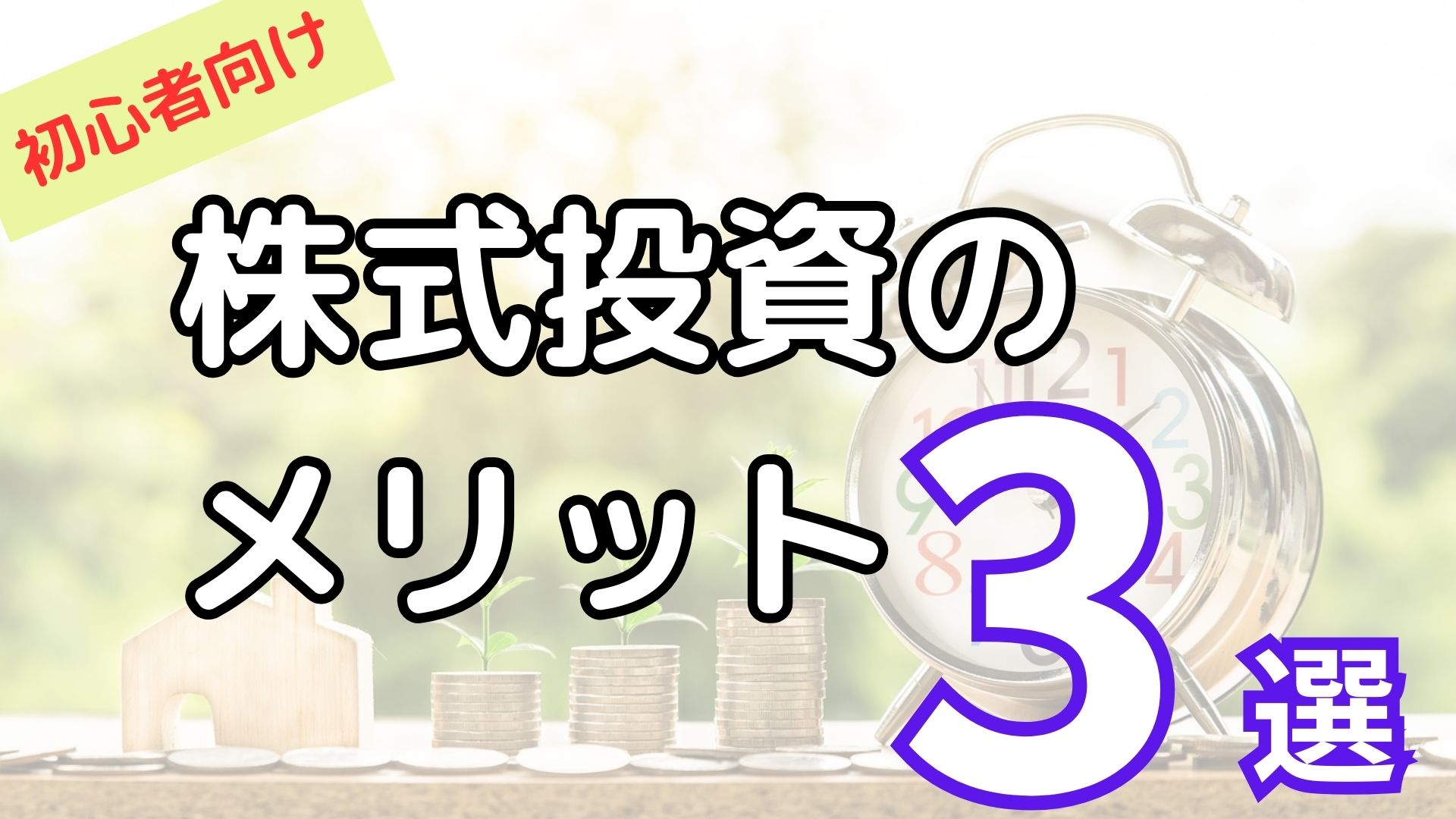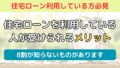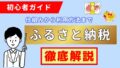現在の日本では、アメリカなど他の先進国に比べて投資をしている国民の割合が低いという特徴があります。その理由として「損をするのが怖い」「お金がなくなるかもしれない」といった負の感情が先行してしまっていることが考えられます。
確かに、株式だけでなく投資信託やその他運用商品は日々価格が変動しており、損失のリスクが潜んでいます。
しかし、株式は単に価格が上がったから儲けた、下がったから損をしたという単純なものではありません。本記事では株式を保有することで株主がどんなメリットを受けられるのかを初心者向けに解説していきます。
株式を保有するメリット
長期的な値上がりが期待できる
株式が長期的に値上がりが期待できる理由には、企業の成長や経済の発展、市場の効率性など、いくつかの要因があります。以下にその主な要因を説明します。
企業の成長
まず、企業の成長が株式の長期的な値上がりに寄与します。企業は新しい技術やサービスを提供したり、効率的な経営を行ったりすることで、売上や利益を増加させ、株主へのリターンを提供します。
特に、成長産業に属する企業や、革新を続ける企業は、将来的に利益を拡大させやすいため、その株価も長期的に上昇する傾向があります。例えば、ITや再生可能エネルギーなどの成長産業に関連する企業は、今後の成長が期待される分野であり、株価の上昇が見込まれることが多いです。
経済全体の成長
次に、経済全体の成長も株式市場に影響を与えます。長期的に経済が成長し続ける限り、企業の業績もそれに伴って向上します。GDPの成長や消費の拡大、雇用の増加など、経済の健全な成長は企業の収益を押し上げ、その結果として株価も上昇します。さらに、インフレに伴って物価が上昇すると、企業の売上が増えることも多く、株価の上昇を促す要因となります。
また、株式市場は効率的であり、投資家が企業の業績や経済の動向に基づいて株価を評価するため、長期的には適正な株価に向けて調整される傾向があります。短期的には株式市場は感情や一時的なニュースに影響されることがありますが、長期的には企業の実力や経済の成長が反映され、株価は徐々に上昇していきます。
以上のように、企業の成長や経済全体の発展、株式市場の効率性などが相まって、株式の長期的な値上がりが期待できるのです。
配当金が受け取れる
株式を保有することで受け取れる配当金は、企業が得た利益の一部を株主に分配する形で支払われるお金です。配当金は株式投資における重要な収益源であり、株主にとっては利益の還元として非常に魅力的な要素となります。
配当金の仕組み
企業が得た利益の一部を株主に還元する方法として、配当金が支払われます。配当金は、企業の財務状況や利益、成長戦略に応じて毎期決定されます。企業が利益を上げても、その全額を内部留保して再投資に回す場合もあれば、利益の一部を配当金として支払う場合もあります。配当金の支払いは、通常、四半期や年単位で行われることが一般的です。
配当金の額は「1株あたり○○円」と定められており、その額に保有株数を掛け合わせることで、株主が受け取る金額が決まります。例えば、1株あたり50円の配当金が支払われる場合、100株を保有していれば、5000円の配当金を受け取ることになります。企業は配当金を支払うことを決定する際に、配当性向(利益に対する配当金の割合)を考慮します。
配当金の意義
配当金は株主にとっての利益還元の一環であり、株式投資の魅力を高める要素となります。特に安定的な配当金を提供する企業は、投資家にとって安心感を与える存在です。高配当株や安定的な配当を続ける企業は、資産運用の一つの方法として選ばれることが多いです。
また、配当金は企業の経営状態を示す指標ともなります。安定した配当金の支払いは、その企業が健全な財務状況であることや、成長余力があることを示唆する場合があります。逆に配当金の減額や停止が発表されると、企業の業績や経営に不安があると受け取られることが多いため、株主にとっては重要な情報となります。
配当金の税金
配当金には税金が課されます。日本では、配当金に対して源泉徴収税が20.315%(2025年3月現在)課せられ、これが自動的に差し引かれた後に株主に支払われます。そのため、受け取る金額は配当金額から税額を差し引いたものとなります。確定申告を通じて、税額を調整することも可能です。
以上のように、配当金の魅力は、株式を売買して得られるキャピタルゲイン(株価の上昇による利益)だけではなく、定期的に安定した収入源を得られる点にあります。
特に、長期的な保有を前提とする投資家にとっては、配当金が安定した現金収入となり、生活資金の一部として活用することもできます。また、再投資によって、配当金が次第に雪だるま式に増えていく可能性もあるため、資産運用において非常に重要な要素となります。
株主優待が付いてくる
株主優待とは、企業が自社の株を一定数以上保有している株主に対して、商品やサービスなどの特典を提供する制度です。この制度は日本独自のもので、投資家に対する感謝の気持ちや、企業のブランド価値向上、株主の長期保有を促進することを目的としています。株主優待は、企業によって内容や提供方法が異なり、多くの企業が魅力的な優待を用意しています。
一般的な株主優待としては、自社製品や商品券、割引券、食事券などがあり、特に飲食業や小売業などでは実施されることが多いです。例えば、オリエンタルランドの株式を500株保有しているとディズニーの1dayパスポートがもらえたりします。もっと身近なところではイオンの株式を100株以上保有していると、保有株数に応じてイオンでの買い物が数%キャッシュバックされます。
株主優待は、配当金とは異なり、現金ではなく物品やサービスが提供されるため、投資家がその企業に対して親近感を持つきっかけとなり、企業にとっても認知度向上にもつながります。また、優待が魅力的な企業の株は、株価に良い影響を与えることもあります。
株主優待を受け取るためには、各企業が定めた基準日に株を保有している必要があり、その基準日を過ぎると優待が受けられないため、株主優待を狙うタイミングを見計らって購入しましょう。
このように、株主優待は株主にとっての魅力的な特典となり、投資判断において重要な要素の一つです。
株式投資をする上での注意点
様々なメリットがある株式投資ですが、実際に投資を行う上での注意点を挙げておきます。
リスクを理解する
株式投資には値動きがあるため、短期的には株価が大きく変動することがあります。値下がりリスクを含むことを理解し、投資の目的やリスク許容度に応じて行動することが重要です。また、どうような出来事が株価に影響するかなど株価を動かす要因についても勉強をしておきましょう。
分散投資を心がける
1つの株式に集中投資をするのはリスクが高いです。上場企業が倒産するケースはごくまれですが、もし現実にそれが起きると保有している資産がゼロになるということです。そのようなリスクを含むことを理解し、投資の目的やリスク許容度に応じて行動することが重要です。
長期的視点を持つ
株式投資は長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。短期的な値動きに一喜一憂せず、企業の成長や市場全体の動向に基づいて投資判断を行いましょう。
感情的な投資を避ける
市場の動きに感情的に反応して売買を繰り返すことは、損失を大きくする原因となります。特に株価が下がって含み損を出している時ほど、「すぐ戻るだろう」という無根拠の期待を持ってしまいがちですが、時には思い切って損切りをすることも大切です。損切りについてはこちらの記事でも解説しています。
関連記事:損切りをするタイミングについて
まとめ
いかがでしたでしょうか。株式投資は単なる値上がり益の期待だけでなく、配当金や株主優待を通して投資家に様々なメリットをもたらします。
株式投資を行う際は、十分な余裕のある資金内でしっかり自分で決めたルールを守って行ってください。
ご覧いただきありがとうございました。